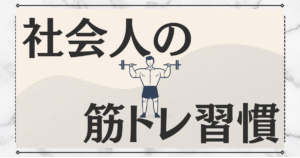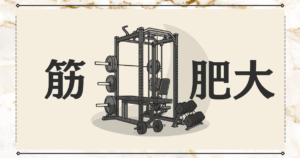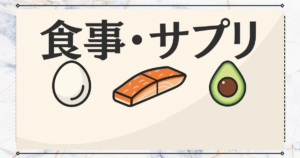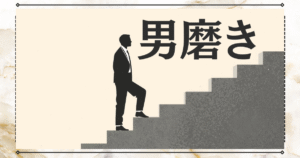はじめに
筋トレを続けていくうえで筋肥大を目指している場合、
- 筋肉が思ったほどつかない
- 体が変わっている実感がない
- 重量があまり伸びない
これらの悩みは常に付きまといますよね。
伸び悩んだ時に最、初に注目するのは
「何キロ持ち上げられるか」という重量の部分だと思います。
しかし、筋肥大を本気で目指すなら、それだけでは不十分です。
筋肉を成長させるためには、
どれだけの負荷を与えられたかという
総負荷量(トレーニングボリューム)が
極めて重要な要素となります。
たとえば、毎週1回ベンチプレスを
高重量で頑張っていたとしても、
週トータルでの総負荷量が少なければ筋肥大は頭打ちになります。
逆に、中程度の重量でも、
適切な回数とセット数を積み重ね、
筋肉に十分な刺激(ボリューム)を与えられれば、
筋肥大を目指すことが可能です。
また、総負荷量を考えるときに
見落とされがちなのが、「回復」です。
刺激を与えるだけでなく、しっかりと回復させる設計をしないと、
オーバートレーニングや伸び悩みにつながります。
この記事では、筋肥大に直結する
「総負荷量」と「回復」をテーマに、
- 総負荷量とは何か
- 科学的に筋肥大に効果的とされる
ボリュームの目安 - 私自身が体重を54kg→67kgまで
増やした3年間で、
どのように総負荷量を調整してきたか - 疲労管理など、継続のための工夫
をわかりやすく紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめ!
- 筋トレをしているのに
成果が出ないと感じている方 - どれくらいの量・頻度で
鍛えればいいのか分からない方 - 科学的根拠に基づいて、
筋肥大を効率よく進めたい中級者 - オーバートレーニングや
疲労の蓄積が気になっている方
筋トレにおける総負荷量とは

筋トレの成果を最大化したいと思ったとき、
まず見直すべき重要な指標が
総負荷量(トレーニングボリューム)です。
これは、筋肉にどれだけのストレスを与えたか
を数値として捉える考え方で、
筋肥大のための基本かつ最重要要素とも言えます。
総負荷量とは、以下の式で算出されます。
総負荷量(kg)= 重量 × 回数 × セット数
たとえば、ベンチプレス60kgを
10回×3セット行った場合の総負荷量は、60kg × 10回 × 3セット = 1,800 となります。
この数値は、1回のトレーニングでその部位に
どれほどの物理的刺激を与えたかを示しており、
筋肉の成長における刺激量の定量的な指標として使っていきます。
なぜ総負荷量が重要なのか
筋肥大のメカニズムには、
- 機械的張力
- 代謝ストレス
- 筋損傷
の3つが関与すると言われています。
このうち、自分でコントロールしやすいのが
「機械的張力」=総負荷量です。
同じ部位を鍛える場合でも、
単に高重量を1セット行うだけではなく、
中重量で回数やセット数を積み重ねて総負荷量を高めることで、
筋肉への刺激を増やすことが可能になります。
特に中級者以降になると、
なんとなくの重量・なんとなくのセット数
では筋肉が反応しづらくなります。
明確な数値として総負荷量を意識することが、
次の成長へのカギになります。
日々のトレーニングにおいて、
使用重量や回数だけでなく総負荷量を記録する習慣を持つことで、
今の自分の成長度や停滞を客観的に把握できます。
- 前回よりも+1セット
- 前回よりも+2回
でも、積み重なれば確実に
総負荷量を増やしていくことが可能です。
ボリュームと筋肥大の関係

「たくさん鍛えれば筋肉はつく」という
この直感は、ある意味で正解です。
しかし、気になるのはどのくらいのボリュームが
最も効果的なのかという点ですよね。
筋トレにおいて、ボリューム(総負荷量)と筋肥大の関係は、
数々の研究によってその関係が研究されています。
ボリュームは筋肥大の「量的ドライバー」
筋肥大に影響を与える要素は大きく分けて3つあります。
- 機械的張力(筋肉にかかる物理的負荷)
- 代謝ストレス(パンプや乳酸による刺激)
- 筋損傷(筋繊維の微細な破壊)
この中でも、機械的張力=ボリュームの蓄積が
最も確実に筋肥大へつながると考えられています。
たとえば、2017年にBrad Schoenfeld博士らが
発表したメタ分析では、
以下のことが明らかになりました。
週あたりのトレーニングセット数が増えるほど、
筋肥大効果は大きくなる傾向にある。具体的には、週10セット以上を行ったグループの方が、
5セット以下のグループよりも明確な筋肥大を示した。
という研究結果が出ています。
ボリュームは足りなさすぎても多すぎても逆効果
ここで注意したいのが、ボリュームには「適量」があることです。
- 少なすぎる
→ 筋肉への刺激が不十分で成長しない - 多すぎる
→ 回復が追いつかず、
オーバートレーニングやケガにつながる
特に中級者以上は、筋肉が刺激に慣れてくるため、
適切な量とタイミングで刺激を与え続ける設計が重要になります。
一般的なボリューム目安(部位ごと/週あたり)
| レベル | 大筋群(胸・背・脚) | 小筋群(二頭・三頭・肩など) |
|---|---|---|
| 初心者 | 10〜12セット | 6〜10セット |
| 中級者 | 12〜20セット | 10〜15セット |
| 上級者 | 20〜25セット以上 | 15〜20セット |
あくまで目安であり、個人差・疲労耐性により調整が必要です。
1~3年目までの方は、
この範囲で基本的には成長をしていくことができると思います。
その理由としては、私自身が現在筋トレ3年目ですが、
各部位のセット数については、
大体この表のセット数内に収まっており
使用重量、筋肉量が伸びているためです。
ボリュームを稼ぐ戦略
ボリュームを効果的に増やすには、
必ずしも「高重量」だけが正解ではありません。
- 中重量(6〜12RM)でのセット数の増加
- スーパーセットやジャイアントセットで密度向上
- 週2回以上の分割で、部位ごとの頻度を上げる
などの工夫により、
質と量を両立しながら負荷を増やすことができます。
筋トレの総負荷量の推移の目安として

筋肥大に取り組むうえで、
どれくらいの量をこなせば筋肉がつくのかという問いは、
初心者から中級者まで誰もが一度はぶつかる疑問です。
ボディメイクにおける最も重要な指標の一つが
総負荷量(トレーニングボリューム)であることは、
簡単にまとめてきましたが、実例がないとわかりにくいですよね。
この章では、わたしが
体重54kgから67kgまで増量した3年間の筋トレ記録をもとに、
各年のトレーニング内容と総負荷量の変遷、
そして成長に繋がった要素を時系列で紹介していこうと思います。
筋トレを始めたての初心者~中級者の方には
参考になると思います。
【1年目】筋トレ初期
筋トレを始めたての頃は、お恥ずかしいながら
胸と背中だけに偏った週8〜12セットの
ボリュームで筋トレをしていました。
私が筋トレを始めたのは、2022年6月、24歳のときです。
当時の体重は54kg、身長は170cmで、いわゆる細身体型で
周囲からガリガリとよく言われてました。
目的は筋肥大とボディメイクで筋トレを始めました。
初期のトレーニングは、
とにかくベンチプレスとラットプルダウンを中心に、
週2〜3回のトレーニングを継続していました。
この頃の総負荷量は、胸と背中にそれぞれ週8〜12セット程度。
総負荷量としては、
- 胸 :2760~3400
- 背中:3600~4000
ほどだったと思います。
肩、腕については、胸と背中の補助で
刺激が入っているはずだと考え、
個別に種目に取り組むことはありませんでした。
また、脚については全くやっていませんでした。
このような内容でも、最初の半年〜1年は、
初心者だったということもあり、
この程度でもしっかり反応しました。
体重は1年で約4kgほど増えて、
体重が60kgいかないくらいになりました。
自分的には、見た目に胸筋が少しついたなと感じられていました。
【2年目】中級者への移行期
2年目に入ると、いろいろな筋トレの情報をみて、
自分の体のバランスが悪いように感じはじめていました。
胸と背中で上半身の前後は鍛えていても、
肩や腕をやっていないため、バランスが悪く、
細く見えるのが気になり始めたのもこの時期です。
そこでトレーニング内容を見直し、
肩に週8セット、腕(二頭・三頭)に週6セットを加えました。
胸と背中のボリュームもそれぞれ週10〜15セットに引き上げ、
トレーニング全体のボリュームが格段に増えました。
この時点で、筋トレの頻度も週3回から週4回に増加しています。
扱う重量も少しずつ増え、
ベンチプレスは100kgをやっと超えたのもこの時期です。
当時の総負荷量としては、
- 胸 :5000~6800
- 背中:7150~8220
- 肩 :2850~3300
- 腕 :1790~2200
この頃から、周囲の人にも
「最近がたい良くなった?」と聞かれることが増え、
自分でも見た目の変化をより実感できるようになりました。
体重としては、2年目終了時点で約65kgほどになっていました。
【3年目】脚トレ導入
筋トレ3年目にしてようやく導入したのが「脚トレ」です。
それまでは脚のトレーニングをやったほうがいいのは
分かってるけど後回しにしていました。
全身のバランスや筋肉の伸びを考えると、
下半身の発達が筋肥大全体を底上げする
と実感するようになりました。
現在では、脚に対しても
週10〜12セットを入れるようにしています。
胸・背中はそれぞれ12セット、肩10セット、腕8セットと、
ほぼ全身を網羅したボリューム設計に移行しています。
3年目の現在は週4~5で筋トレをしており、総負荷量は以下です。
- 胸 :6800~7429
- 背中:8500~9000
- 肩 :3600~4230
- 腕 :2790~4000
- 脚 :4280~6480
加えて、この時期からアプリでのトレーニング記録、
総負荷量管理を開始しました。
それまでは「なんとなく前回と同じかちょっと増やした」という
感覚ベースの管理だったのが、数字を通して
正確にボリュームを比較・計測できるようになりました。
正直、もっと早くノートやアプリで
管理していればよかったなというのが感想です。
見返したときに、停滞し始めた時期もわかりやすくなりますし
なにより、毎回の筋トレで総負荷量を
しっかりと意識することができます。
成長を実感できた理由と今後の課題
成功要因としては、以下が大きいと考えています。
- 肩・腕・脚といった後回しにしがちな部位も
しっかりボリュームを配分した - 週トータルでのボリューム設計を
意識するようになった - データ記録により、
過去との比較・評価ができるようになった
また、以下の点を初期のころから
意識できていればよかったなと感じています。
- 脚のトレーニング開始が遅れたことにより、
スクワットが他の種目に比べて弱い - 睡眠や疲労の管理が甘かった時期には、
ボリュームをこなしても伸び悩んだ - 疲労によるセット数のばらつきが
パフォーマンスに影響することも
現在の成果と目標
現在の体重は67kg(体脂肪率12%前後)です。
BIG3で扱える重量は、
- ベンチプレス:120kg
- デッドリフト:170kg
- スクワット :115kg
まで伸ばすことができました。
見た目の変化はもちろん、自信や日々のモチベーションの面でも、
筋トレの恩恵を強く実感しています。
今後は脚トレもしっかりとやっていかないとな
と感じているとともに、
疲労管理や回復戦略も大事であることを感じています。
年間を通して安定してボリュームを
確保できる状態を目指しています。
疲労管理、回復の重要性

筋トレで筋肉を大きくしたいなら、
まずどれだけ刺激を与えられるかの総負荷量が問われます。
そして、同じくらい重要なのが、
「回復が追いついているか」です。
ボリュームを意識することは重要ですが、
回復と疲労管理の質も成長速度に大きく関わっています。
回復力の土台の強化
総負荷量を増やしていくと、疲労もたまりやすくなっていきます。
そして、回復が追いつかず、
オーバートレーニング状態になることもあります。
総負荷量の底上げと、回復とのバランスを上手にとるために、
以下の要素も考慮していくことが大切です。
睡眠
- 筋肉の成長ホルモンは、
深い眠り(ノンレム睡眠)中に多く分泌される - 6〜8時間の質の高い睡眠が、頻度増加の鍵
栄養
- トレーニングによって破壊された筋肉は、
十分なタンパク質とカロリーがないと
回復できない - 特に増量期は、消費カロリー+300〜500kcal程度
の摂取を心がける
自律神経の回復
- 高頻度でトレーニングを行うと、
交感神経優位が続き、
精神的ストレスや倦怠感が出やすくなる - この状態が慢性化すると、
筋出力の低下や睡眠障害、
集中力の低下など悪循環につながる
疲労のセルフケアのおすすめ
私自身、トレーニングを週4〜5回行うようになってから、
疲労と回復のバランスが非常にシビアになった
と感じています。
特に普通に社会人として仕事をしている以上、
翌日の全身のだるさ、集中力の低下などの見えない疲労が
パフォーマンスに影響してしまうこともあります。
そんな中で私は、CBD(カンナビジオール)による
疲労管理を取り入れるようにしています。
CBDは、麻由来の成分でありながら
THCのような精神作用はなく、
合法で使えるリカバリーサポート成分
として注目され、以下のような効果が期待できます。
- 睡眠の質の改善
(入眠しやすくなる/深く眠れる) - 筋肉痛や炎症の緩和
- 精神的ストレスの軽減(自律神経の安定)
特にトレーニング後の入浴後や就寝前に
CBDオイルを摂取することで、
翌朝の疲労感が軽くなったと感じています。
翌日に疲れを残さないことが、
結局は総負荷量の維持・向上にもつながります。
疲労管理については、こちらの記事でまとめているので
ぜひ参考にしてみてください!
-

-
【筋トレ×CBD】ストレス、睡眠の質の管理の重要性
2025/11/13
まとめ
今回は「総負荷量」と「回復」についてまとめてきました。
総負荷量(ボリューム)= 成長のベースラインとなります。
筋肉は、「刺激された量」に対して成長します。
この量を数値化したのが、
総負荷量(重量 × 回数 × セット数)です。
今まで、総負荷量を意識していなかった方は、
下記の点を見直すだけでも成長速度が変わってきます。
- なんとなく3セットではなく、
目的に応じた週間のセット数を意識 - 「今日は頑張った」ではなく、
前週比でどれだけボリュームを上げられたか - 初心者〜中級者であれば、
部位ごとに週10〜20セットを目安に設計
数字で管理することで、
トレーニングを計画的な成長へと変えられます。
また、回復の質も大切です。
負荷の高い総ボリュームも、回復してこそ意味があります。
睡眠・栄養・ストレス管理の3つの柱が崩れると、
せっかくの努力が報われにくくなってしまいます。
- 質の高い睡眠で、成長ホルモンを最大活用
- 十分なPFCバランスとカロリー摂取で、
筋の材料を確保 - 疲労や炎症を抑えるためのCBDなどの活用で、
日々のリカバリー効率UP
私自身もとにかくやりまくって、
回復が追いつかなかった時期には
明らかに記録の伸びが鈍化しました。
逆に、睡眠改善などを見直したタイミングで、
扱う重量・ボリュームが安定し、疲労のブレが小さくなりました。
総負荷と回復のために、
明日からできる3ステップは以下を意識してください。
- 今のトレーニングボリュームを「数値化」する
→ 週あたりのセット数・重量・回数を
アプリやノートに記録 - 頻度とボリュームのバランスを再設計する
→ 各部位を週2回、10〜20セットを目安に
分割法を調整 - 回復の質を上げる習慣を導入する
→ 睡眠時間の確保、CBDやマッサージ、
ストレッチなどをルーティン化
筋肉をつけて、かっこいい体を目指すのは、
決して天性の資質ではありません。
どれだけ努力したかよりも、どう努力を設計したかが大事です。
私も脚トレを後回しにしたことで長く停滞しましたが、
総負荷量の記録と頻度設計、回復戦略を見直したことで、
筋肉を大きくすることができています。
総負荷量は目に見えて管理しやすい数値指標なので
まだ取り入れていない方は、
ぜひ取り入れて筋トレをしてみてください。