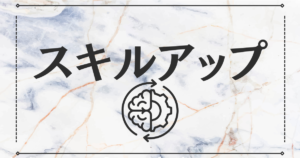はじめに
Pythonである程度コードが書けるようになってくると、
少しずつ実践的なことに挑戦したくなってきますよね。
私自身も、座学的な知識だけではなく
そろそろポートフォリオや副業に活かせるコードを
書いていこうと思い、
簡単な自動化スクリプトやWebアプリにチャレンジしていました。
実務を意識するうえで必須となるのが、
エラーでプログラムが想定外の挙動をとらないように
考慮することです。
プログラムが予期せぬ動作をとったときに
発生している問題を例外と言います。
どのような時に起こるかというと、
以下が学習したてではよくあります。
- 入力された値が想定と違っていた
- 0で割ってしまった
- 存在しないファイルを開こうとした
こうした例外と呼ばれる問題は、
どんなにシンプルなコードでも起こり得ます。
Pythonにはこれらのエラーをうまく処理し、
落ちにくいコードを書くための仕組みが
しっかり用意されています。
それが今回のテーマである 「例外処理」 となります。
今回は私自身が「これは覚えておくのは必須」と感じた
try-except文の基本から、
- よくあるエラーの種類
- エラー発生時の情報の取り出し方
- 複数の例外処理方法
まで、Pythonにおける例外処理の基礎と実用パターンを
まとめていきます。
この記事はこんな方におすすめです!
- エラーに対して、よくわからないまま print() で
確認しているという方 - プログラムが突然止まってしまう経験がある方
- エラーにも対応できる
「信頼性の高いコード」を目指したい方 - 副業や実務でも通じる最低限のエラー対応力を
身につけたい方
第1章:なぜ例外処理が必要なのか
Pythonのコードを書き始めたばかりの頃は、
学習教材やサンプルコードが正常に動く前提で進んでいくので、
エラーに遭遇することはあまり多くないかもしれません。
でも、いざ自分でコードを書くようになると、
エラーの連発に襲われることが増えていきます。
たとえば、以下のようなシンプルなコードに
「0」を入力するとどうなるでしょうか?
x = int(input("数字を入力してください: "))
print(10 / x)プログラムの実行結果は、
ZeroDivisionError: division by zeroとなり、この時点で強制終了してしまいます。
これがまさに「例外(エラー)」が発生した状態です。
例外処理が書かれていないコードは、
- エラー1つで全体が止まる
- ユーザー体験が悪くなる
- 実務では信用されないコードになる
一方で、例外処理をしっかり書くと、
- 起こりうる問題に備えられる
- 予測不能な動きが減る
- ユーザーにもわかりやすい
エラーメッセージを出せる
このように、例外処理は「強いコード」への第一歩となります。
そもそも例外とは
例外とは、コード自体に文法的な間違いはないけど、
実行時に想定外の問題が起きてしまった状態を指します。
- 存在しないファイルを開こうとした
- リストの範囲外の要素を参照した
- ゼロ除算をしてしまった
- 文字列を数値に変換しようとした など
これらはすべて、プログラム実行時に発生する
実行時エラー(Runtime Error)です。
try-except で“強制終了されない”コードに変える
先ほど、例として取り上げた「0除算」でエラーになるコードに、
例外処理を加えてみるとどうなるでしょうか。
try:
x = int(input("数字を入力してください: "))
print(10 / x)
except ZeroDivisionError:
print("0で割ることはできません!")例外処理の書き方は、次の章で詳しくまとめますが、
このように書くだけで、エラーが発生しても
プログラムが強制終了することはなくなります。
また、「0で割ることはできません!」
というメッセージを表示し、
何が起きたかをわかりやすく伝えることもできます。
これが「例外処理」の力です。
第2章:try-except構文
Pythonの例外処理はとてもシンプルでありながら柔軟性が高く、
少し使い方を知るだけで、実用レベルの堅牢なコードが
書けるようになります。
基本構文として、
try:
# エラーが起こるかもしれない処理
except エラーの種類:
# エラーが起きたときの処理たとえば、整数の入力を求める場面で
よくある「型変換エラー」の対処を見てみましょう。
try:
age = int(input("年齢を入力してください: "))
except ValueError:
print("数字を入力してください!")このように、エラーが発生する可能性
のある処理を try: に入れ、
その後 except: でエラーを補足して、
プログラムを止めずに処理を続けることができます。
複数のエラーを補足する
場合によっては、1つの処理の中で
複数の種類の例外が起こることもあります。
try:
num = int(input("数字を入力してください: "))
result = 10 / num
except ValueError:
print("整数を入力してください。")
except ZeroDivisionError:
print("0では割れません!")このように except を複数並べることで、
エラーごとに異なる対応ができます。
すべての例外をまとめて処理する
場合によっては、「どんなエラーでもいいから一括で処理したい」
という場面もあります。
そんなときは、except: のあとに
エラーの種類を指定せずに使うこともできます。
try:
# いろいろな処理
except:
print("予期しないエラーが発生しました。")ただしこれはすべてのエラーを飲み込んでしまうため、
本来気づくべきバグも見逃してしまう恐れがあります。
実務や副業で使うコードでは、
エラーの種類を明示的に指定するのが原則です。
例外情報を変数として取得する
Pythonでは、例外の詳細情報を取得してログに残したい場合、as を使ってエラーオブジェクトを受け取ることができます。
try:
with open("data.txt") as f:
content = f.read()
except FileNotFoundError as e:
print(f"ファイルが見つかりませんでした: {e}")こうすることで、エラーの内容を
ユーザーやログに具体的に出力できて、
あとで調査しやすくなります。
else / finallyでの例外処理
try の後に、except だけでなく else や finally を組み合わせることもできます。
elseは例外が出なかったときだけ
実行されるブロックとして記述します。
try:
num = int(input("整数を入力: "))
except ValueError:
print("数字じゃないです!")
else:
print(f"あなたの入力は {num} です。")また、finallyは例外が起きても起きなくても、
必ず最後に実行したい処理を記述します。
try:
print("処理中...")
1 / 0
except ZeroDivisionError:
print("エラー発生")
finally:
print("終了処理します")finally はファイルのクローズ処理や接続の切断処理など、
最後に必ず行いたい処理を書く場所として便利です。
第3章:よくある例外の種類と特徴
Pythonでプログラムを書いていると、
初心者のうちは、特に高確率で遭遇する
「お決まりのエラー」があります。
この章では、私自身も実際に遭遇したエラーを中心に、
よく出る例外の種類とその意味、原因、対処方法
をまとめていきます。
ValueError:型が違う
代表的なケースとしては、
想定されている引数の型と
実際の受け渡された型が違う場合に発生します。
age = int("twenty")int()に文字列"twenty"を
渡しているため、
数字に変換できずにエラー発生try-exceptで補足して、
入力を再促すのが一般的な対処法
ZeroDivisionError:0で割られている
除算時に、0で割った場合に発生します。
result = 10 / 0- 除算前に分母が0でないか
ifで判定する - または
try-exceptで包んで、
安全な処理に切り替える
FileNotFoundError:ファイルが見つからない
open関数など、ファイル操作をする際に
対象のファイルが存在していない場合に発生します。
with open("not_exist.txt") as f:
content = f.read()- 例外発生時の見直しポイントは、
ファイルのパスが正しいか確認 - コードとしては存在確認をしてから読み込む、
またはtry-exceptで補足
IndexError:範囲外の要素を参照
リストやタプルなど、indexを用いてアクセスする変数にたいして
存在していないindexや範囲外の値を指定することで発生します。
lst = [1, 2, 3]
print(lst[5])len関数でリストの長さを確認してからアクセス- もしくは
try-exceptで回避
KeyError:存在しないキーを参照
ディクショナリにおいて、存在していないキーで
要素を取得しようとすることで発生します。
data = {"name": "Taro"}
print(data["age"])dict.get("key")を使えば、
存在しないキーでもNoneを
返してくれるので安全
第4章:raise文とassert文を使ったエラー制御
前の章までで「起こってしまったエラーへの対処法」
を学びましたが、
今度は 「あえて自分でエラーを起こす」
という考え方を紹介します。
実は意図的にエラーを出すことで、
コードの信頼性を高めることも可能です。
ポイントとして、
raiseを使えば、
自分のルールに違反する入力に対して
明示的に例外を出せるassertを使えば、前提条件を
簡潔にチェックできる
(主にテストやデバッグ用)- どちらも「コードの信頼性や保守性」を
高めるために重要なツール
raise文:自分で例外を発生させる
raise 文は、
「ここで明示的に例外を発生させたい」
というときに使います。
例として、年齢が0以下なら例外を出すといった場合です。
def set_age(age):
if age <= 0:
raise ValueError("年齢は正の整数である必要があります。")
print(f"年齢は {age} 歳です。")このように、業務ルールやビジネスロジックに
合わない値を防ぐ目的で使われます。
よくある使いどころとしては、
- 数値が負の値であってはいけない場合
- 必須のデータが渡されていないとき
- 特定の条件が成立していないと処理できない場合
assert文:前提条件をチェックする
assert 文は、
「この条件が真であるべきだ!」
というときに使います。
条件が False の場合、
自動的に AssertionError を発生させます。
例として、リストの長さを事前にチェックする場合などです。
data = [1, 2]
assert len(data) == 3, "リストの長さが正しくありません"条件がFalseだった場合、以下のような出力となります。
AssertionError: リストの長さが正しくありませんassertを使うポイントとして、
- デバッグやテスト時のチェック用に使うのが基本
- 本番環境では
python -Oオプションを使うとassertは無視される(注意)
第5章:例外処理のベストプラクティスと注意点
Pythonの例外処理には非常に柔軟な機能がありますが、
自由度が高いぶん、避けたほうが良い使い方も存在します。
私自身も実際にやりがちだった失敗例も交えながら、
例外処理のベストプラクティスと注意点を紹介します。
ベストプラクティス(やるべきこと)
1. 具体的な例外クラスを補足する
# NG例(Exceptionでなんでもキャッチ)
try:
process()
except Exception:
print("なんかエラー")
# OK例(具体的なエラーを補足)
try:
process()
except ValueError:
print("値が不正です")2. 最小限の範囲でtry-exceptを使う
# NG例(tryの範囲が広すぎる)
try:
a = int(input("数値を入力: "))
b = a * 2
print(b)
except ValueError:
print("数値を入力してください")
# OK例(最小限の処理をtryに)
try:
a = int(input("数値を入力: "))
except ValueError:
print("数値を入力してください")
else:
b = a * 2
print(b)3. ログ出力や再raiseで情報を残す
try:
do_something()
except ValueError as e:
print(f"エラー発生: {e}")
raise # 再スローして上位で処理避けるべき例外処理
1. すべての例外を無視する
try:
dangerous_code()
except:
pass # これは危険!エラーがあっても気づかないコードになります。
必ず原因の把握や、ログ出力をするべきです。
2. Exceptionで全部キャッチしてそのまま続行
try:
something()
except Exception:
print("なんか失敗したけど、まぁいいか")原因が不明瞭なまま続行すると、
致命的なバグが埋もれやすくなります。
3. 複雑なロジックをtryブロックにまとめすぎる
tryの中で複数の処理をまとめてしまうと、
どの処理が原因かわからなくなります。
必ず、「失敗する可能性のある最小単位」に
try-exceptをかけると原因がわかりやすくなります。
第6章:まとめ & 次回予告
今回は「例外処理」をテーマに、
エラーに強いコードの書き方について学んできました。
学び始めのうちは難しそうに見えるかもしれません。
それでも、ひとつひとつの構文や考え方を理解すれば、
確実に自信を持って扱えるようになります。
特に私が学んで感じたのは、
try-except構文の柔軟さと、
raiseやassertによる制御の便利さです。
また、例外処理はエラーを防ぐためだけでなく、
ユーザーや開発者に正しくエラーを伝えるためにも
大切な役割を果たしています。
今回の学びポイント
try-except構文でエラーをキャッチし、
安全に処理を継続できるraiseで意図的に例外を出すことで、
ルール違反を事前に検知できるassertはデバッグやテスト用の
便利なチェックツール- 入力処理やファイル操作には、
具体的なエラーを想定した設計が重要
ここまでで、Pythonの基本文法を一通り学んできたので、
次に取り組むのは 、ポートフォリオとして
実践的なWebアプリ開発をしていこうと考えています。
そこで選んだのが、Pythonの人気Webフレームワークである
Django(ジャンゴ)。
次回からは以下のようなテーマを扱っていく予定です。
- Djangoとはどんなフレームワーク?
- Webアプリ開発の全体像とは?
- なぜDjangoを学ぶのか
- Djangoでポートフォリオをつくれるのか
これまで学んできた知識をどう活かせるのか、
私自身の“実践記”として、リアルな気づきとともに
発信していきたいと思います。
▶次回の記事はこちら:
-

-
Django??未経験がPythonフレームワークを学ぶ
2025/10/1