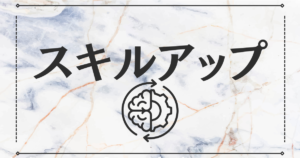はじめに
Pythonの学習を進めていく中で、
コードの量が増えてくると
- もっと整理して書きたい
- ファイルを分けたい
と感じる場面が増えると思います。
プログラミングが初めてだと、
すべての処理を1つのファイルに詰め込んでしまい、
少しずつ手に負えなくなることも多いです。
そんな時にPythonで押さえてほしいのが
モジュールとパッケージという考え方です。
これらは、簡単に言えば
コードを他のファイルに分けて、
必要なときに呼び出せる仕組みです。
小さな関数の再利用から、複数人での共同開発、
副業案件でのコード整理に至るまで、
モジュールとパッケージを理解して使えるかどうかで、
開発のしやすさが大きく変わります。
今回は、私が実際に学んだモジュールと
パッケージの基本や使い方を紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめです!
- Pythonを学んでいて、
1ファイルにコードが長くなってきた方 importの仕組みがよくわからないまま
使っている方- モジュールとパッケージの違いを
明確に理解したい方 - 実務や副業で使える
「ファイル分割テクニック」を知りたい方
第1章:モジュールとは
Pythonにおけるモジュールとは、
Pythonコードを1つのファイルにまとめ、
再利用可能な部品にしたもののことです。
拡張子 .py のファイルがそのままモジュールとして使えます。
たとえば、utils.py というファイルに関数を定義しておけば、
他のPythonファイルからその関数を、
import で呼び出せるようになります。
こうすることで、共通の処理を何度も書く必要がなくなり、
コードの整理や再利用性が格段に向上します。
モジュールを使うことでできること:
- 関数や変数、クラスを
他のファイルから呼び出せる - プロジェクトを複数のファイルに分割でき、
見通しが良くなる - チームや副業での作業でも、
コードの分担がしやすくなる
組み込みモジュールと自作モジュール
Pythonには、最初から用意されている
便利な組み込みモジュール(標準モジュール)と、
自分で作成する自作モジュールの2種類があります。
組み込みモジュールの例:
- math
数学関数(平方根、三角関数など) - datetime
日付と時刻の操作 - random
乱数生成 - os
ファイルやディレクトリ操作 - sys
インタプリタ設定、引数取得など
自作モジュールの例:
# ファイル:my_utils.py
def greet(name):
return f"こんにちは、{name}さん!"自作モジュールは組み込みモジュール以外の
すべてのものが当てはまります。
import構文
モジュールを使うには、import文を使います。
基本の使い方は以下の通りです。
import モジュール名 # 例:import math
from モジュール名 import 関数名 # 例:from math import sqrt
import モジュール名 as 別名 # 例:import datetime as dt第2章:import構文のテクニック
まずはimportの基本パターンを押さえることが大切です。
Pythonでは、モジュールを使うことで
他のファイルに定義された関数やクラスを再利用できます。
まずは基本的なimportの3つの書き方を整理しましょう。
① 単純なimport:
import math
print(math.sqrt(25)) # → 5.0② from ... import ...:
特定の関数だけを直接使いたいときに便利、
名前空間が短くなる。
from math import sqrt
print(sqrt(25)) # → 5.0③ import ... as エイリアス名:
長いモジュール名を短くしたり、別名で呼びたいときに使う。
import datetime as dt
now = dt.datetime.now()
print(now)モジュールの__name__属性
Pythonモジュールには、
特殊変数 __name__ が用意されています。
これはモジュールが 、
直接実行されたか or 他のモジュールからimportされたか
を判断するために使われます。
例として、sample.pyの挙動をあげていきます。
def greet():
print("こんにちは!")
if __name__ == "__main__":
greet()python sample.pyとして直接実行__name__ == "__main__"
→greet()が実行される
- 他のファイルから実行
import sample
→__name__ == "sample"となりgreet()は実行されない
ポイントとして、この仕組みにより、
テスト用コードと本番用コードを
1つのファイルに共存させることも可能になります。
組み込みモジュールと外部モジュール
Pythonには初めから使える標準モジュール(組み込み)と、pipなどで追加する外部モジュールがあります。
今回の対象は主に前者ですが、知っておくと実務にも役立つ分類です。
| 分類 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 組み込みモジュール | math, datetime, os | importだけで使える |
| 外部モジュール | requests, numpy, pandas | pipでインストールが必要 |
補足:with文とモジュールの関係
with文は、モジュールの機能を使って
「自動で処理の前後を制御する」ための構文です。
たとえば open() 関数(ioモジュール由来)などで
利用するのが代表的です。
with open("sample.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
content = f.read()
print(content)
この場合、with文を使うことで、
ファイルの自動クローズが保証されます。
これは、ファイル操作系のモジュールでは
非常によく使われています。
importの注意点
- インポートはなるべくファイルの先頭に
まとめて書く
→ 可読性・保守性のために
一般的なPythonのスタイル - 多重インポートの心配は不要
→ Pythonは同じモジュールを2回以上
読み込んでも1回だけ実行します - 名前の衝突に注意
→ 自作関数や変数と同じ名前のモジュールを
使うとバグの原因になる
第3章:パッケージと __init__.py
これまで学んできたモジュールは
「1つの .py ファイル」でした。
それに対してパッケージとは、
複数のモジュールを1つにまとめたフォルダ構造のことです。
簡単にいえば、モジュールの集合体がパッケージです。
パッケージ構成の基本例として、
myapp/
├── __init__.py
├── utils.py
└── models.pyこのような構成になっていると、myappという名前のパッケージとして他からimportできます。
パッケージのポイントは、__init__.py がフォルダ内に存在することです。
このファイルがあることで、そのフォルダが
パッケージとして認識される仕組みです。
__init__.py の役割
- パッケージとしての認識
※Python 3.3以降は省略可だが、
あった方が無難 - 初期化処理や外部に公開する
モジュールや関数の指定ができる
__init__.pyのファイル内の記述例として、
# __init__.py の例
from .utils import greet
from .models import Productこうすることで、myapp パッケージをimportしただけで
greet や Product が使えるようになります。
第4章:importの使い方での注意点
モジュールやパッケージの使い方に慣れてきたら、
もう一歩進んで実務でトラブルにならないimportの使い方
を知っておくことが大切です。
この章では、Pythonを使った副業案件や実務開発でも役立つ、
import構文の実用ポイントや注意点を具体的に見ていきます。
importはファイルの先頭に書くのが基本
Pythonのコードスタイルとして、
import文はファイルの冒頭にまとめて書くのが一般的です。
# 推奨される書き方
import os
import sys
from datetime import datetime
# 実際の処理はそのあとに
print(datetime.now())これにより、コード全体の依存関係がすぐにわかるため、
可読性や保守性が向上します。
名前の衝突(上書き)に注意
モジュール名や関数名を
変数名と同じにしないよう注意が必要です。
NG例として、
import random
random = 5 # 上書きされる!
print(random.randint(1, 10)) # エラーになる!このように、名前が衝突してしまった場合、
解決策として、以下を意識しておくことが大切です。
- モジュールに別名をつける(エイリアス)
- 変数名と重ならないような命名規則を意識する
if __name__ == "__main__"の使い方
モジュールにテスト用コードを書くときは、
この書き方が基本となることが多いです。
# sample_module.py
def greet():
print("こんにちは")
if __name__ == "__main__":
greet() # 直接実行時だけ動くこの仕組みにより、モジュールとしてimportされたときに
余計な処理が実行されるのを防げます。
モジュールの検索パスとsys.path
Pythonはモジュールを探すとき、以下の順にパスを確認します。
- スクリプトがあるディレクトリ
- 環境変数
PYTHONPATHで指定されたパス - 標準ライブラリのディレクトリ
- サイトパッケージ(外部ライブラリ)
これらはsys.pathで確認できます。
import sys
print(sys.path)自作モジュールが見つからないなど認識されていない場合、
このリストを確認、調整することで解決できることが多いです。
よくあるエラーと対処法
| エラー名 | 原因と対処方法 |
|---|---|
ModuleNotFoundError | ファイル名・パスを確認。sys.pathの確認も有効 |
ImportError | モジュールは見つかったが、その中の関数が無い |
AttributeError | import先の関数名・クラス名が間違っている |
ValueError: attempted relative import beyond top-level package | 相対インポートが正しくない、単体実行されているケース |
第5章:副業や実務でのモジュール活用
Pythonの基礎学習を進めていくと、
いつかは副業で使ってみたい、
実務でも活かせそうと思う場面が訪れます。
私自身もその1人で、勉強しながら
どのように業務や副業で使えるだろうと常に考えています。
私が考えるモジュールの活用場面としては
以下のようなシーンがあるのかなと現時点では感じています。
スクレイピングのコード整理
PythonでWebサイトの情報を収集する
スクレイピング系の副業では、
複数の処理(リクエスト送信、HTML解析、データ保存など)を
関数単位に分け、モジュール化することで
保守性が格段に上がります。
scraper_project/
├── __init__.py
├── fetcher.py # データ取得
├── parser.py # HTML解析
└── saver.py # ファイル保存1つのファイルに詰め込むとごちゃごちゃしてしまう処理も、
モジュールに分けることで読みやすく、使い回しやすくなります。
チャットボットや自動化ツールの構成整理
LINE botや、Slack botなどの自動応答ツール開発では、
以下のようにファイルを分けることがよくあります。
message_handler.py→ メッセージの判定処理api_client.py→ APIとの通信処理config.py→ 設定情報管理
このようにモジュール単位で設計できると、
機能追加や修正が非常にしやすくなります。
チーム開発での役割分担に有効
複数人での開発では、
「〇〇の処理はAさんが担当」
「設定系はBさんが管理」
などとモジュールごとに担当者を分けるケースが多くあります。
このとき、明確にファイルが分割されていれば、
Gitなどのバージョン管理ツールでも衝突が起きづらく、
効率よく開発できます。
テストのしやすさが上がる
各機能をモジュール化しておけば、
pytestやunittestなどのテストフレームワーク
を使って単体テストが簡単に書けます。
テストを書く文化が根づいている現場では、
関数やクラスの再利用性を高めること以上に、
「テストしやすいかどうか」=構成の良さ
と見られることもあるためです。
第6章:まとめ&次回予告
今回は、Pythonの学習を一歩進める上で欠かせない
モジュールとパッケージの基礎について、
私自身が学んだことをまとめてご紹介しました。
- モジュールは
.pyファイルとしてコードを
分割、再利用できる便利な仕組み import文の使い方を理解すれば、
他ファイルの関数やクラスも自由に活用可能- パッケージはモジュールをまとめたフォルダ
__init__.pyで初期設定や公開範囲を制御
正直、最初はimportを
何となく使っている状態になると思います。
しかし、基礎を抑えることで
開発を効率化するための強力な道具として
活用することができます。
次回は、今回の「モジュール」の学びをさらに広げて、
Pythonが標準で備えているライブラリ(標準ライブラリ)
を中心に学習、まとめていく予定です。
- よく使われる標準ライブラリ
(datetime, random, osなど)の
具体的な活用方法 - 学習で用いたライブラリ
- 業務で使われることが多い便利なライブラリ
これから副業や実務でPythonを活かしていきたい方にとって、
ライブラリを使いこなせることは大きな武器になります。
▶次回の記事はこちら:
-

-
Python入門:学習用で覚えたいライブラリについて
2025/8/23