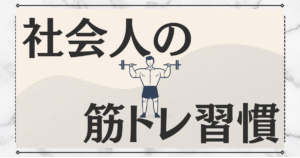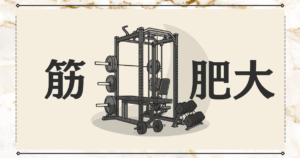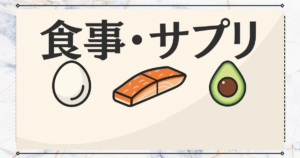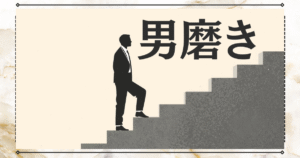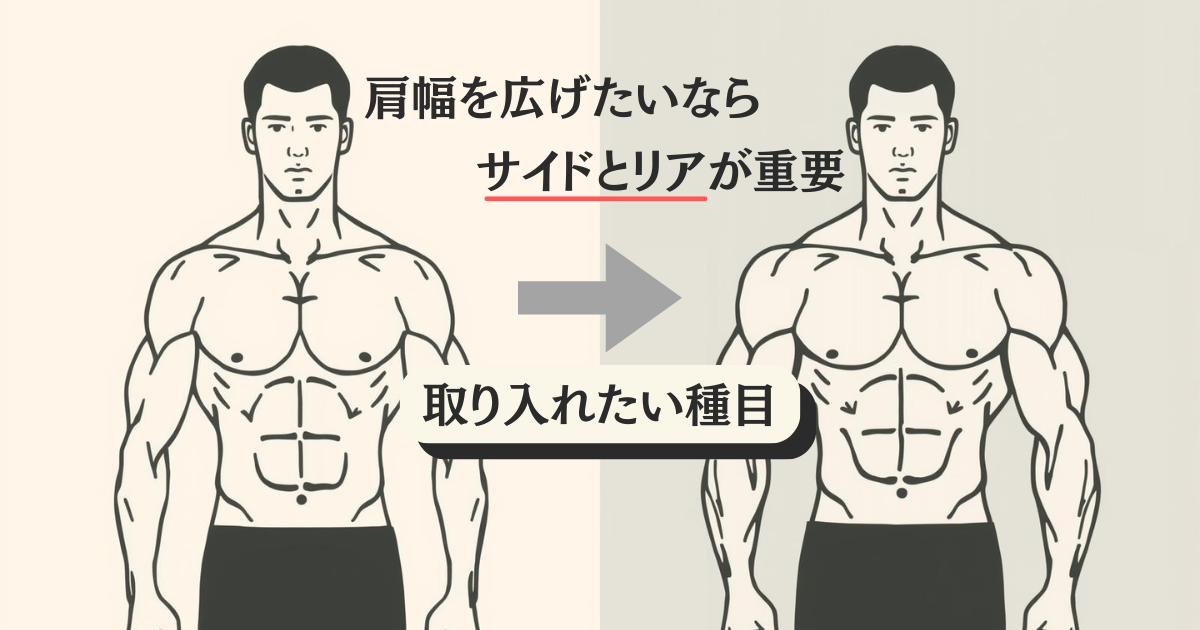はじめに
筋トレを続けて、ハマっていくと、よりこだわりたくなる部位が
肩(三角筋)ではないでしょうか。
筋トレにハマった多くの方が、
- もっと肩を大きくしたい
- メロンのような肩を目指したい
- 逆三角形の体型のために肩幅を広げたい
と胸や背中、脚などの大きな筋肉だけでなく
肩にも理想のイメージを持てるようになっていきます。
しかし、胸や腕の筋肉が成長にくらべ難しい部位です。
実際に肩トレを本格的に始めてみても、
以下のように感じる方も多いです。
- サイドレイズやリアレイズを続けているけど、
肩幅が変わらない - 胸や腕は太くなったのに、肩だけ丸みが出ない
肩は筋肥大の変化が見えにくい部位であり、
トレーニング方法を工夫しないと
成果を実感しづらいのが現実です。
もちろん、まずはショルダープレスやサイドレイズなどの
基本種目を押さえることが重要です。
ですが、私自身も肩を大きくしたいなと思ったときに
基本種目ばかりで肩トレに伸び悩んでいたのも事実です。
そこで今回は、肩幅が変わらない原因と、
三角筋中部・後部を狙う種目、
肩幅を広げ丸みを出すための基本的な考え方を紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめです!
- 肩幅を広げたいが、
今のトレーニングに伸び悩んでいる - サイドレイズやリアレイズをやっているが
成果を感じにくい - 三角筋中部・後部を重点的に鍛えたい
- 肩トレのフォームや種目選びを見直したい
なぜ肩トレは成果が見えにくいのか

まずはじめに、肩は胸や腕と違い、
成長を実感しづらい部位であると感じている方が
多い部位になります。
その理由として、考えられるのが以下の3つの理由です。
- 肩関節は日常的に腕を支える持久力型の筋肉
- 肩は「腕を常に支える」役割が大きく、
意識的に負荷をかけなくても、
日常生活でも使われるため、
他の部位と比べた時に
刺激への反応が鈍くなりやすい - 胸や背中のようにわかりやすい形の筋肉
ではないため、1~2か月程度では
劇的な見た目の変化が起きにくい
- 肩は「腕を常に支える」役割が大きく、
- 意識しにくく、負荷が逃げやすい
- 特にリアレイズなど後部狙いの種目では、
僧帽筋に負荷が逃げやすく難しい - 胸などの様にマッスルマインドコネクション
も意識しにくい
- 特にリアレイズなど後部狙いの種目では、
- 鍛えるべき部位が細かい
- ベンチプレスやショルダープレスなど、
肩に刺激が入るといっても三角筋前部が中心 - 肩幅や丸みを出すためには中部・後部への
刺激も確保することが重要
- ベンチプレスやショルダープレスなど、
三角筋の部位ごとの役割
肩全体は三角筋の3部位(前部・中部・後部)
で構成されています。
そのなかでも、肩幅やアウトラインを変える鍵は中部と後部です。
- 三角筋前部
- 直接肩幅に関与しないが、
前から見た迫力には重要 - 中部・後部ばかり鍛え、前部を疎かにすると
バランスが悪く見えるため注意が必要
- 直接肩幅に関与しないが、
- 三角筋中部
- 肩の外側にボリュームを作りを作る
- 肩幅を広く見せる主役
- 三角筋後部
- 後ろ姿の丸みと厚みを作り、
立体的なアウトラインを作る要 - 立体的な肩幅に見せる
- 後ろ姿の丸みと厚みを作り、
肩の成長を実感するためには、
それぞれ狙った部位をピンポイントで効かせるトレーニング
の積み重ねが必須です。
まずは中部・後部の基本種目となる
サイドレイズ、リアレイズを押さていくことが重要です。
基本種目だけでは、成長が停滞していると感じている方には
アップライトローやリアデルトをこだわるのがおすすめです。
肩幅を出すための基本種目

肩幅を広げたいと考えたとき、多くの方が最初に取り組むのが
サイドレイズ(三角筋中部狙い)と
リアレイズ(三角筋後部狙い)です。
これらはシンプルですが、肩トレの基礎であり、
正しいフォームで継続すれば確実に効果があります。
現時点で、肩トレを本格的に始めていないのであれば、
ショルダープレスに加え、サイドレイズとリアレイズで
前・中・後部に全体的に刺激を入れるところから始めましょう。
サイドレイズ(三角筋中部)
狙いと効果:
- 肩の外側(三角筋中部)をメインに刺激する
- 肩幅を広く見せる主役種目
フォームとポイント:
- フォーム
- ダンベルを両手に持ち、
体の横に自然に下げる - 肘を軽く曲げたまま、
肩の高さまでゆっくり持ち上げる - 下ろすときも勢いをつけず、
コントロールする
- ダンベルを両手に持ち、
- ポイント
- 反動を使わず、狙った筋肉だけで上げる意識
- 肘が手より高くなるイメージで動かす
- 回数:10〜15回×3セット
(最後は限界近くまで追い込む)
リアレイズ(三角筋後部)
狙いと効果:
- 肩の後ろ(三角筋後部)を鍛え、
後ろ姿の立体感を作る - サイドレイズと並んで、
アウトライン作りに欠かせない
フォームとポイント:
- フォーム
- ベンチに座るか、上体を前傾させる
- ダンベルを両手に持ち、腕を体の下に垂らす
- 肘を軽く曲げたまま、
横方向に開くように持ち上げる - 肩甲骨を寄せすぎず、後部だけを意識
- ポイント
- 重すぎる重量はNG(僧帽筋に負荷が逃げる)
- 軽めの重量で、三角筋後部だけに集中
- 回数:12〜15回×3セット
変化が見えにくいと感じた時
肩のトレーニングは、胸トレで行うベンチプレスなどの様に
負荷を乗せる特定部位を意識するのが難しいです。
そのため、あまり変化を感じられない時は
以下の2点を見直してみてください。
- 肩以外の筋肉を使ってしまっている
- 反動を使いすぎると
僧帽筋や腕に負荷が逃げる - まずは軽めの重量でフォーム重視が基本
- 反動を使いすぎると
- 中部・後部への意識が弱い
- 動作中にどの筋肉を使っているか
を意識できていない - ネガティブ動作などで負荷が乗っている意識
を持つことが大切
- 動作中にどの筋肉を使っているか
サイドレイズやリアレイズは肩トレの基本です。
しかし、これらを続けていても肩幅が変わらないと
感じるタイミングが来てしまう方も多いと思います。
私自身も最初はこの2種目だけで鍛えていましたが、
ある程度発達したところで伸び悩みました。
私の考えでは、この2種目では
あまり高重量を扱えないためだと考えています。
同じように肩トレをはじめて、
サイドレイズ、リアレイズに取り組んでいるのに
頭打ちを感じている方は、この後紹介する
アップライトローとリアデルトを取り入れてみてください。
これらの種目は基本種目よりも重量を扱いやすく、
今までの刺激と異なるアプローチができます。
私自身もこれらの種目を取り入れてから、
肩の丸みや幅の成長を実感することができています。
アップライトローの活用法

まず、私がアップライトローを取り入れた理由は
ショルダープレス以外で肩の横・後部で
高重量を扱える種目を取り入れたいと考えたためです。
アップライトローでは、
- サイドレイズでは扱いにくい高重量を使える
- 三角筋中部に加え、三角筋後部、僧帽筋上部も
動員され、肩周り全体に強い刺激を与えられる
この種目を取り入れてから、
まず肩トレ後のパンプ感が明らかに変わりました。
しかし、高重量を扱えて、
肩トレの切り札になりそうなアップライトローですが、
実は「肩のインピンジメント症候群(肩の挟み込み)」
のリスクがあると言われる種目でもあります。
私自身、アップライトローを取り入れるようになって
1年以上経過していますが、
インピンジメントは起こしていません。
そのため、適切なフォームと重量設定を守れば
安全に行えうことができると考えています。
リスク回避ポイントとして、
- 肩幅程度のグリップ幅にする
- 狭すぎるグリップは、
肩関節に負担がかかりやすいため
- 狭すぎるグリップは、
- 肘を肩より高く上げない
- バーやダンベルを持ち上げる高さは、
みぞおち~鎖骨あたりで止める - 僧帽筋へ負荷を逃がしにくくもなる
- バーやダンベルを持ち上げる高さは、
- 無理な高重量を使わない
- 高重量といっても、6~8回程度の回数を
こなせる重量で行う
- 高重量といっても、6~8回程度の回数を
これらのリスク回避ポイントに合わせ、
私はアップライトローであえて少し反動を使い、
高重量を扱う方法を取り入れました。
理由は以下の通りです。
- サイドレイズでは扱えない重量で
中部に強い張り感とパンプ感を得られた - 完全にコントロールする動作だけよりも、
刺激が強く肩の成長を感じやすかった
もちろん、反動を使う場合も可動域を維持しつつ
怪我に注意する必要があります。
しかし、他の筋肉同様に肩を大きくするためには、
重量を扱っていくのが大切です。
肩後部をピンポイントで狙うリアデルト

肩幅を広げたいと考えると、
多くの人が中部ばかりを重視しますが、
後部の発達も肩のアウトラインを完成させる上で欠かせません。
三角筋後部が発達すると、
- 後ろ姿の丸みが増し、肩全体が立体的に見える
- 横から見たときにも肩の張り出しが強調される
実際、私自身も後部をしっかり鍛えるようになってから、
理想の丸みに近づけるようになりました。
特に後部の種目では、リアデルトマシンに切り替えてから
後部の成長を強く感じました。
リアデルトのメリットとして、感じているのは以下の3点です。
- 肩後部に負荷がピンポイントで入る
- ダンベルで起こりがちな
僧帽筋への負荷逃げが少ない
- ダンベルで起こりがちな
- フォームが安定しやすい
- マシンが軌道を固定するため、
後部を動かすのが苦手でも
正確に後部を狙いやすい
- マシンが軌道を固定するため、
- マシンで軌道が安定するので高重量を狙える
- 肩で高重量を扱うのは少し怖さもある中で、
マシンなら軌道固定で怪我のリスクを
抑え重量を扱う刺激を入れられる
- 肩で高重量を扱うのは少し怖さもある中で、
リアデルトの効果的なやり方
フォームのポイントと回数設定はあくまで私の取り入れ方ですが、
この方法を試してから肩の後部の張りが強くなったので、
とてもおすすめです。
私のリアデルトのマシンの使い方は、シートに座るものではなく
いわゆる立ってリアデルトを使う方法になります。
- フォームのポイント
- シートには座らず、
おでこをパッドかマシンにつける - ハンドルは軽く握り、
肘をやや外側に開く意識 - 動作を押し出すときは、肘と手首で押し出す
- 肩甲骨はなるべく固定し、寄せすぎない
- シートには座らず、
- 回数とセット数
- 8~12回の5セット
- 5セット目で8回ギリギリとなる重量
個人差はもちろんあると思いますが、
私はリアレイズを行っていた際は、
後部よりも僧帽筋に効いてしまう感覚が強く、
思うように発達を感じられませんでした。
しかしリアデルトマシンを取り入れてから、
肩後部のパンプ感を感じやすく、
翌日の筋肉痛も明確に後部にくるようになりました。
肩の丸みを強調したい方は、ぜひリアデルトを
後部のメイン種目として取り入れることがおすすめです。
肩のアウトラインを完成させるための注意点

肩幅を広げたい=中部・後部だけでは不十分です。
肩幅を広げる、逆三角形の体型を作るという目標では、
三角筋中部・後部が最重要です。
しかし、ここで注意すべき落とし穴があります。
それは、前部(三角筋前部)を完全に無視してしまうことです。
前部を鍛えないとバランスが崩れる理由
- 肩全体の迫力が弱く見える
肩幅が広くても、前側のボリュームが
不足していると、正面から見たときに
「薄い肩」に見える - 姿勢が悪く見えることも
肩前部が弱すぎると、胸とのバランスが崩れ、
縮こまってに見える原因になる場合もある
肩トレにこだわるほど「中部・後部重視」に偏りがちですが、
全体のアウトラインを意識するなら、
前部も最低限鍛える必要があります。
前部を鍛えるおすすめ種目としては、
王道のショルダープレスがおすすめです。
ショルダープレスでは、肩の前部を中心に
マシンでもダンベルなどのフリーウェイトでも
高重量を扱うことができます。
怪我が怖い方は、マシンやスミスでの
ショルダープレスが非常におすすめです。
肩幅を広げたい方も、肩幅に繋がらないからと言って
前部を疎かにするのは絶対にやめましょう。
バランスを意識し、横幅とアウトラインの両方を強調するためにも
最低限、前部も鍛えるようにしましょう。
バランスの良い肩は、Tシャツを着たときに
「肩で服が張る」ような迫力が出せるようになります。
まとめ
肩トレで肩幅を広げたいのに、結果が出ない時、
最大の理由は中部・後部が十分に鍛えられていないことです。
肩は日常生活で常に腕を支える役割があり、
持久力に優れた筋肉です。
胸や腕と同様の考え方でのセットやメニューでは反応しにくく、
強い負荷を意識的に各部位ごとに、
与えなければ筋肥大が起こりにくいという特徴があります。
肩幅を変えるための優先順位として、
- 三角筋中部
- 肩の横幅を直接広げる主役
- サイドレイズ+アップライトローで
高重量刺激がおすすめ
- 三角筋後部
- 肩のアウトラインと後ろ姿を作る
- リアデルト(マシン)で重量を扱うのが
停滞打破にもおすすめ
- 三角筋前部
- 肩全体の迫力を作る
- 肩幅を広げる観点でもバランスを意識して
鍛えることが重要
私も以前、サイドレイズとリアレイズだけを続けていて
「肩幅が広がらない」と感じていました。
しかし、アップライトローとリアデルトを取り入れたことで
肩の丸みや幅の成長を感じることができました。
もちろん、基本種目であるサイドレイズ、リアレイズで
基本的な肩の土台ができていたことも要因として考えられます。
それでもアップライトローとリアデルトは
素晴らしい種目だと感じています。
- アップライトロー
- 少し反動を使い、高重量を扱う
- 中部のパンプ感が強くなり、
肩の張りが増した
- リアデルト
- マシンのおかげで後部にピンポイントで
刺激が入れやすい - アウトラインがはっきり出るようになった
- マシンのおかげで後部にピンポイントで
肩トレは成果が出にくい部位ですが、
中部・後部に正しい刺激を続ければ確実に変わります。
私自身、アップライトローとリアデルトを取り入れてから、
筋トレを一緒にしている友達から
肩幅が広がったと言われるようになりました。
肩トレにこだわりだすと、より筋トレは楽しくなります。
まずは1セットでもいいのでサイドレイズを始め、
次にアップライトローとリアデルトを習慣化してみてください。