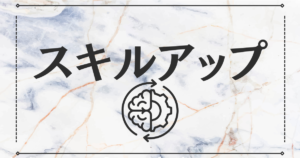はじめに
DjangoでWebアプリ開発を始めるとき、
バックエンド側の根幹を担うのが views.py です。
しかし、はじめて触れてみると、
- このファイルに何を書けばいいのか
- テンプレートとの違いがよく分からない
と戸惑ってしまうことも少なくありません。
views.pyは、ユーザーからのリクエストを受け取り、
適切なレスポンスを返す司令塔 のような役割を持ちます。
テンプレートとしてのHTMLを表示させるのも、
フォームから送られたデータを処理するのも、
最終的にはこのViewの中で決定されます。
この記事では、views.pyの基本的な役割や、
私が学習する中でつまずいたポイント、
実際の具体的な書き方などをまとめて紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめです!
- DjangoのViewが何をしているのかまだ曖昧な方
- HTML(Template)は作れるけど、
処理の流れが理解できていない方 - 実際のWebアプリを動かすために、
views.pyの基礎を固めたい方
第1章:views.pyの役割
まず、DjangoはMTVモデルと呼ばれる仕組みで動いています。
- Model:
データベースとのやり取りを担当 - Template:
ユーザーに見せる画面(HTML)を担当 - View:
処理の流れをコントロールする司令塔
この中で views.py が担うのは、
ユーザーのリクエストを受け、適切な処理を行い、
その結果をレスポンスとして返す部分です。
1. リクエストとレスポンスの橋渡し
Webアプリの基本的な流れはシンプルです。
- ユーザーがURLにアクセスする
(リクエストを送る) - Djangoが
urls.pyを見て
「どのViewを呼ぶか」を決定 - Viewが必要な処理を行う
(データ取得や計算など) - 処理結果をHTMLやJSONなどの
レスポンスに変換して返す
このWebアプリの処理一連の流れの中で、
③と④を担うのがviews.pyです。
例えば「Hello Django!」と表示するだけのページを作る場合、
views.pyには次のように書きます。
from django.http import HttpResponse
def hello_view(request):
return HttpResponse("Hello Django!")- ユーザーが
/hello/にアクセスすると、hello_viewが呼び出されるようにurls.pyに定義しておく - ここで文字列を直接レスポンスとして返すと、
ブラウザにそのまま表示
とてもシンプルですが、これがViewの基本形です。
2. Templateとの関係
Webアプリとして作成する場合、
「Hello World!」のような文字列を直接返すのではなく、
テンプレート(HTMLファイル)を組み合わせて
画面を表示することがほとんどです。
そのため、Viewでは対象のテンプレートに
必要なデータをセットで受け渡す役割を担います。
from django.shortcuts import render
def signup_view(request):
return render(request, 'signup.html')この場合、Viewは
「signup.htmlというテンプレートを探して返す」
という役割を果たします。
テンプレートについては、
こちらで私の学習をもとに別記事にしていますので
参考にしてみてください。
-

-
DjangoのテンプレートでデータをHTMLに埋め込む
2025/9/12
3. 関数ベースビュー(FBV)とクラスベースビュー(CBV)
DjangoのViewには大きく2種類あります。
- 関数ベースビュー(FBV)
- 上の例のように
Pythonの関数として書く形式 - シンプルで理解しやすい
- 上の例のように
- クラスベースビュー(CBV)
- Djangoが用意したクラスを
継承して作る形式 - 例えば
ListViewやDetailViewを
使うと、記事一覧や記事詳細を
少ないコードで実現できる
- Djangoが用意したクラスを
私は、まずポートフォリオの作成では
FBVでViewを作成しています。
私と同じようにPythonやIT自体未経験の場合、
FBVでまずは基本の流れを押さえて、
慣れてきたらCBVを学ぶと理解がスムーズになると思います。
第2章:つまずいたポイント
views.pyはDjangoアプリの中心的な存在です。
しかし、学習を始めたての頃は、
何を書けばよいかで迷いやすいです。
ここでは、私がつまずいたポイントを整理します。
1. ViewとTemplateの違いがあいまい
Viewという名前から画面表示(ビュー)だと思っていたため、
HTMLの画面表示に関わるものを、views.pyとtemplatesのどちらに書けばいいのかが
最初はあいまいで、疑問も多い状態でした。
それぞれの役割として、
- View:
処理の流れを制御する場所
(データを集めてテンプレートに渡す) - Template:
見た目を担当する場所
(データを画面に表示する)
例えば、ユーザー一覧を表示するときの処理の切り分けは、
- Viewで「データベースからユーザーを取得」
- Templateで「取得したユーザー名をリスト表示」
このように、処理と見た目を混ぜないことが
それぞれの役割を曖昧にせず、
つまずかないためのポイントです。
2. POSTデータが取得できない
画面からの操作でフォームを送信したとき、
バックエンド側でデータ操作をしたいのに、
そのデータがviews.pyで受け取れないという点もつまずきました。
典型的な誤りとして、
def signup_view(request):
username = request.POST['username'] # KeyErrorが出るこの場合、フォームが送信されていない状態でも request.POST['username'] を実行しており、
エラーが発生しています。
解決策としては、まず リクエストの種類を判定することです。
def signup_view(request):
if request.method == "POST":
username = request.POST.get('username')
# データを使った処理
return render(request, 'signup.html')また、request.POST.get() を使うと、
キーが存在しない場合もエラーを出さずに None を返すので安全です。
3. TemplateDoesNotExistエラー
ポートフォリオ作成のために、よく遭遇したのが
TemplateDoesNotExist というエラーです。
主な原因として、
- テンプレートファイルの場所が間違っている
- settings.pyの
TEMPLATES['DIRS']に
パスを追加していない - アプリの
templates/フォルダ構成
が正しくない
解消するために、意識したいポイントとして
app_name/templates/app_name/template.htmlのように
アプリごとにtemplatesを作る
(ベストプラクティス)- render関数の第2引数には、
フォルダ構成に合わせた正しいパスを書く
4. HttpResponseとrenderの使い分け
Webアプリのレスポンスの返却方法として、
単純に文字列を返す HttpResponse と、
テンプレートを使う render の違いで混乱しがちでした。
- HttpResponse:
とてもシンプル、学習やテストに便利 - render:
テンプレートにデータを渡すときに使う、
実際のアプリ開発ではほとんどこちら
学習初期やサンプルコードではまず HttpResponse("Hello Django!") が多いですが、
ポートフォリオなど、実際のWebアプリを作る場合、 render() を最初から使うようにすると
スムーズに理解できます。
5. URLとViewの紐づけミス
単純ミスではありますが、urls.pyで指定したView関数名と、views.pyの関数定が一致しておらず
エラーの原因が迷宮入りしかけることもありました。
# urls.py
path('signup/', views.sign_up, name='signup')
# views.py
def signup_view(request): # 名前が一致していない
...この場合、Djangoはurls.pyの定義をもとに、views.pyの「sign_up」という関数を探します。
しかし、存在しないためエラーになります。
関数名のミスやスペル間違いは、
気を付けたいあるあるの落とし穴です。
第3章:実際のViews.pyの定義
views.pyの役割や注意点を理解したところで、
実際の定義のためのコードで振り返ってみます。
DjangoにおけるViewの基本から、
フォーム処理やクラスベースビュー(CBV)の使い方までを
段階的にまとめていきます。
1. テンプレートを使った画面表示
Webアプリのほとんどでは、
画面表示にHTMLテンプレートを使って画面を表示します。
from django.shortcuts import render
def index_view(request):
return render(request, 'index.html')この場合、Djangoは templates/index.html
を探して返します。
ただテンプレートを表示さえるだけではなく、
データをテンプレートに渡して、
そのデータで動的に画面の値を変えたい場合、
render関数の第三引数に受け渡したいデータを渡します。
def greet_view(request):
context = {"name": "太郎"}
return render(request, 'greet.html', context)テンプレート側では、受け渡されたデータのキー名で
アクセスすることで値を利用可能です。
<p>こんにちは、{{ name }}さん!</p>Viewがデータを集めてテンプレートに渡す
という役割を果たしていることがここでわかります。
3. GETとPOSTの処理
フォームからデータを送る場合、
リクエストの種類を判定する必要があります。
def signup_view(request):
if request.method == "POST":
username = request.POST.get("username")
password = request.POST.get("password")
# ユーザー登録処理をここで書く
return HttpResponse(f"{username} さんを登録しました!")
else:
return render(request, 'signup.html')- GET:フォームを表示する
- POST:送信されたデータを処理する
このように、リクエストの種類の条件分岐で
処理を切り替えるのがViewの典型的なパターンです。
4. 複数の処理を分けて管理
処理が増えると、1つのViewに全部書くのは非効率です。
- 「入力フォームの表示」と「送信後の処理」を
別のView関数に分ける - 「一覧表示」「詳細表示」「新規作成」など、
役割ごとに関数を作る
例として、ブログアプリの一部を抜粋すると
def post_list(request):
posts = Post.objects.all()
return render(request, 'post_list.html', {"posts": posts})
def post_detail(request, post_id):
post = Post.objects.get(id=post_id)
return render(request, 'post_detail.html', {"post": post})Viewを小さく分けると、可読性と保守性が向上します。
5. クラスベースビュー(CBV)の導入
Djangoには、よく使う処理を効率化するために
クラスベースビュー(CBV) が用意されています。
記事一覧を表示するためのListViewを参考にすると、
from django.views.generic import ListView
from .models import Post
class PostListView(ListView):
model = Post
template_name = 'post_list.html'
context_object_name = 'posts'urls.py側では、
from django.urls import path
from .views import PostListView
urlpatterns = [
path('posts/', PostListView.as_view(), name='post_list'),
]ListViewを継承することで、Post.objects.all()の処理を自動で行うDetailView,CreateView,UpdateView
などもあり、同じように使える
まず関数ベースビュー(FBV)で
基礎を理解することが大事ですが、
実装の効率を上げていくために、
CBVを段階的に取り入れるのはありです。
第4章:まとめ
今回は、Djangoの views.py について基本を
私が学習した内容をもとに記事をまとめていきました。
views.pyは、バックエンド側の
アプリ全体の動きを決める役割です。
DjangoでWebアプリを作成する際に、
フロントエンドの画面側だけでなく、
バックエンドでのデータ操作も重要です。
そのためには、このviews.pyを押さえることが大切です。
ポートフォリオとしては、まずは簡単なViewからはじめ
次にフォーム入力を受け取って処理するViewを実装してみると、
Djangoらしい流れが理解できると思います。
Viewを理解すれば、
Djangoでできることの幅が一気に広がります。
実際に動かしながら学ぶことが、理解の近道です。
私もポートフォリオ用のWebアプリができたら
また記事にしていこうと思います。